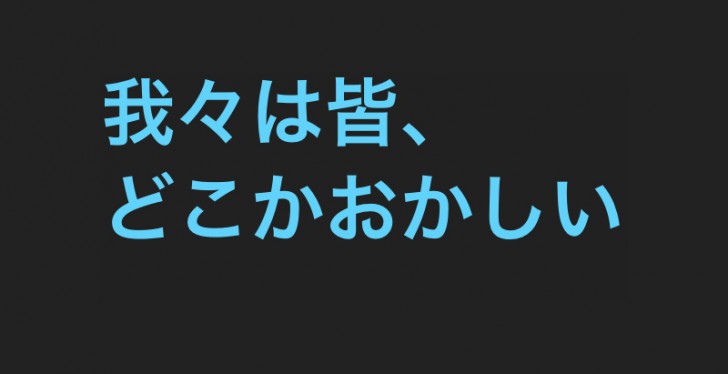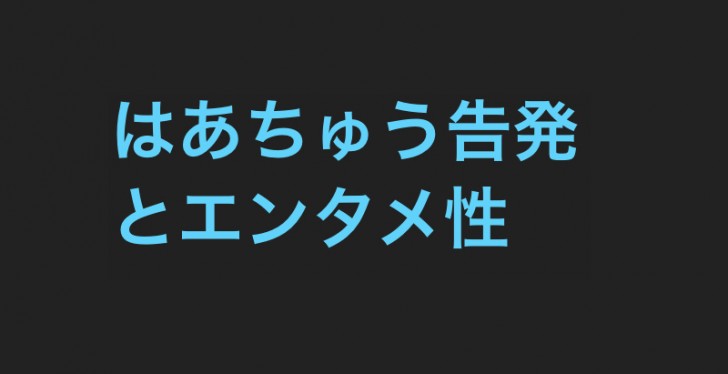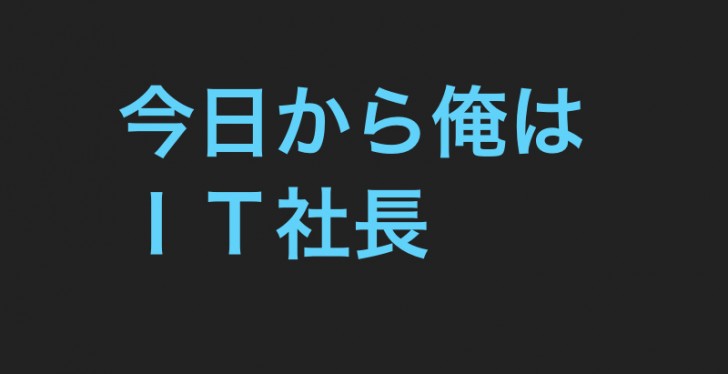問題を起こさない少年時代を送ってきた。
高校を卒業するまで、僕はほとんど1つも表立った問題を起こさなかったと言っていい。
かといって、ことさらに大人に従順だったという記憶もない。単に、問題を起こすきっかけが存在しなかったという方が適切かもしれない。
10代の僕は無気力に人生を過ごしていた。膨れていく自意識を抑え込みながら、置かれた集団に馴染むことに必死で、何かに夢中になることなどなかったと言っていい。
自由な時間は、漫然と消費した。中高時代、近所のゲームセンターや古本屋にどれだけの時間を注ぎ込んだか想像もつかない。
そもそも、子どもが「問題を起こす」というのは難しいことだ。「問題を起こさない」よりもずっと明確な理由を必要とする。
問題を起こすためには、身の周りの大人に対するアピールにせよ、あるいは個人な欲望にせよ、働きかけたい理由がないといけない。
それは例えば、「大人の態度を改めさせたい」 だとか「自分の意志を認めて欲しい」だとか、「とにかく目先の金が欲しい」だとか、多岐に渡るんだろうけれど。いずれにせよ、そういう理由があるから問題を起こすのだ。
僕には、問題を起こすための何の理由もなかった。
大人や体制が好きだったわけではない。むしろ嫌いだっただろう。だけど、積極的に問題行動に出るような理由もなければ、エネルギーもなかった。
そう考えると、問題を起こす子というのは、少年らしい素晴らしさに満ちあふれている。彼らは「何かがある子」なんだ。強い欲望とか理想とかエネルギーとか、そういうものがある子なんだ。
僕には、そういったものが何もなかった。「何もない子」だったから、問題を起こさない子だった。
そんな僕でも、一度だけ、「反省文」を書かされたことがあった。
今日は、その話をしよう。
「保健」の授業、薄っぺらい教科書の下で
中学校の頃、「保健」という座学の科目があった。
今となっては、あの科目で何を扱っていたのかほとんど記憶にない。性教育の時間があったことだけは漠然とおぼえているが、それ以外の時間に何をやっていたのかは分からない。
ペーパーテストがあったのは確かだから、病気の話とか、人体の話とか、そんなことをやっていたのだろうかと思われる。
いずにれせよ、僕が記憶している保健の授業の印象は、妙に薄い教科書と、平坦に響くテノールの体育教師の声だけだ。
中学2年生のある日の保健の授業、とにかく退屈を持て余していた僕は、机に入れていた読みかけの小説を読んでいた。
保健の授業の内容は全く覚えていないが、この時読んでいた小説のことは克明に覚えている。「暗いところで待ち合わせ」という小説だった。当時出たばかりのこの小説は、数年後に映画化されることになる。
アイデアに満ちた素晴らしい設定が冴える傑作である。穏やかで心温まる文学的表現を味わいつつ、異様な設定と驚きに満ちた展開にドキドキしながらページをめくることができる、二面性のあるホントウに素晴らしい小説だ。
教師の退屈すぎる授業を聴きながら、続きがあまりに気になったので、保健の薄っぺらい教科書の下に隠して、この小説を読んでいた。
15分ほどもそうしていただろうか。事件の真相がポツリポツリと見え始めた頃に、教室の後ろのドアが開いた。ドアが開く音を聞いて反射的に小説を机の中にしまう。
しかし、ドアから入ってきた老齢のクラス担任は、僕のところに歩いてきて「出せ」と言った。休み時間に自分の担任学級の様子が気になった彼は、ドアの窓から教室を覗き込んで、読書に夢中だった僕を発見したのだろう。
彼におとなしく小説を渡すと、彼はその小説を、ハリセンみたいにして、僕の頭を小突いてから黙って立ち去った。ああ、取り上げられると続きが読めなくなってしまう、と思った。
保健の授業が終わった後、授業をしていた体育教師に呼び出された。小説を取り上げたクラス担任ではない。授業をしていた体育教師にである。彼はクラス担任とコミュニケーションを取ってないが、僕が小説を取り上げられるくだりを見ていて事情を察したのだろう。
「うわ、面倒だな」と思った。このパターンは、後で担任教師から二重に怒られる可能性がある。この学校の教師たちの職務分担がいかにいい加減かということを重々承知していた僕は、同じ説教を食らうことを嫌に思った。
また、仮に一回で済むとしても、できれば嫌味ったらしいこの体育教師ではなく、さっぱりと叱るクラス担任の方に怒られたかったなと思った。
「オレの授業はそんなにつまらなかったですか?」
今でもハッキリ思い出せる。説教の第一声は、これだった。語尾が敬語なのも含めて、大いに嫌味ったらしい。
この体育教師は、嫌味ったらしい物言いが大いに癇に障る。体育教師らしからぬタイプだった。
僕は中学1年生の間、この男が担任の学級にいたから、この男の性向は概ね理解していた。どうせ、何を言っても嫌味が返ってくる。
彼の第一声へどう回答したかは覚えていない。「いえ……」とか、そのくらいの回答だっただろう。
とにかく、僕の回答いかんに関わらず「成績は良くても、授業を聞くという基本的な行動ができないヤツはダメ」「お前のそんな態度だと○○高校には受かるはずがない」といった内容の嫌味を色々と言われた。
10分間の休み時間を全部使って説教されて、ようやく解放された。この後、クラス担任にも説教されるのか、とか、でもそれを通過しないと本を返してもらえないしなあ、とか、とても憂鬱になったことを覚えている。
放課後、僕を呼び出したクラス担任の教師は意外なことを言った。
「反省文を書いてきなさい」と。
体育教師に怒られた話は伝わっていたらしく、彼からのお説教はなかった。代わりに、反省文という宿題が課されてしまった。
僕は、「なんだかおおごとになったな」と思った。と同時に、「僕への当たりが厳しいのでは?」とも。
当時、僕の在籍していた公立中学はお世辞にも環境が良いとは言えず、やれ万引きだやれ暴力事件だと、多くの生徒が色んな事件を起こしていた。
同級生は中学生ながらに、自動車を盗んで家庭裁判所に送られるというなかなかパンクな悪事をやっていたし、彼は授業中に堂々とマンガを読んでいたような気がする。
彼はそれでも何も言われないのに、僕は反省文を書かされるのか……と思った。ジャイアンがたまに良いことをするとすごく良いやつに思えることを俗に「ジャイアン効果」と言ったりするけど、僕の場合は「逆ジャイアン効果」だな、と。
反省文は、筆が進まなかった
僕は、今も昔も文章を書くのが得意である。
筆は速い方だし、テキトウな内容をでっち上げるのも得意だ。読んでいない本の読書感想文を30分で書いたこともある。
けれど、この反省文は、筆が進まなかった。原稿用紙2枚、普段ならものの15分で埋まる分量なのに。
大して悪いことをしたとは思っていない。普段から問題行動をしている生徒なら、特に目をつけられるでもなく処理されるであろう問題行動。
そして、あの体育教師の、嫌味っぽい遠回しな説教。反省文を書こうと思うと生理的に嫌悪感が湧き上がってきた。
「面倒だ」とか「モチベーションがない」とかそういう話ではなく、「書きたくない」文章を書かなければならなかったのは人生であの時だけだっただろう。
「書きたくない」文章を書くのはあれほど筆が進まないのだと、14歳の僕は初めて知った。
そんなワケで、不当であると思える処分への反発として、嫌味っぽい体育教師の説教への反発として、書きたくない反省文は結局書かずに翌日を迎えた……
と、なれば青春っぽい行動でとても気持ちいいのだけれど、そうはならなかった。
自分の中に、嫌悪感や反骨心といったものが芽生えた機会だったけれど、それはすっかり抑え込んで、社会との折り合いをつけてしまった。
結局、僕は「何もない子」であり続けた。問題を起こさない子であり続けたのだ。
「筆が進まないなあ」という気持ちを1時間ばかり抱えてほとんど一文字も書かずに過ごした後、僕は「まあテキトウな言葉を並べ立てておこう」というスイッチが入り、そこからはあっという間に反省文を完成させた。ベタな文章ばかりが並んだ、なんの中身もない反省文になった。
翌朝、反省文を提出しに行った。老齢の担任教師は反省文に目を通した後、読みかけの小説をあっさり返してくれた。
なんだったんだろうな、と思った。全く意味のない反省文を書かせるバカバカしい茶番。
茶番に腹が立ったけど、無事に小説の続きを読めることを嬉しく思った。返ってきた本のしおりが変なところに移動していたのも、あまり気にならなかった。
僕は、昔から器用なタイプだったのだろう。
これは茶番だという怒りや、不当なものに対する憤りは湧いてくるけれど、「まあ、そこそこに付き合っておこう。本返して欲しいし」と、テキトウに折り合いをつけることができる。
よく言えば器用で老成された子どもだったと言えるだろうし、悪く言えば何もない子どもだったと言えるだろう。
筆が進まないものを書かされた苛立ちや、不必要に嫌味っぽい体育教師への反発はすぐに忘れ、「暗いところで待ち合わせ」の素晴らしいオチと読後感に浸ることになった。
あんな反省文は、もう書かない
あれから、10年以上の時が経った。
この10年間で、色々なことがあった。大学に入ってからの僕は、少々自分の意志を持って動き回るようになり、それに伴って少々問題児になった。
学生団体を作ったり崩壊させたり、卒業研究をサボりまくって卒論を3日で書くハメになったり、大学院の推薦を卒業直前で蹴って、卒業と同時に無職になったりした。
社会人になってからは、訴訟を起こされたり、大風呂敷を広げた事業をあっさりやめてしまったりした。
何もない子であった僕は、すっかり何かある子になり、「問題を起こす子」になった。
いや、その頃の僕はもう立派な大人だ。「問題を起こす人」になったという方が正しい。
世間的に見れば、これは褒められた変化ではない。
「昔はヤンチャしてたけど、今はすっかりマジメになった」という人はすごく真人間な感じがするが、「昔はおとなしかったが、今はヤンチャをする人になった」という人は、ろくでもない人間という感じがする。
だけど、僕は良い変化をしたと思っている。中学生の頃よりも、今の方がずっと人生が楽しい。
今の僕なら、あんな反省文はあっさり足蹴にするだろう。
「書きたくないし、こんな無意味なものを書かないといけない集団なら、二度と付き合わなくていい」と、はっきり言える。
生理的に嫌な、嫌味っぽい説教をするあの人への反発心は、そのまま行動に移せる。「ええ。あなたの授業は全然面白くありませんでした。もう少し創意工夫をなさったほうがよろしいのでは?」と、嫌味っぽい返しができる。
まあこれは単に僕の思想的な変化だけでなく、立場や力関係の変化によるところが大きいのだけれど。
もちろん今でも、大人として「反省文」を書かないといけない時もある。社会と折り合いをつける作業は、相変わらず存在する。
でも、ホントウに嫌なら書かなくてもいいし、実際に「嫌だから」という理由で書くのを放棄したことが度々ある。
問題を起こさない子だった頃の僕は、もういない。今の僕は判断の上で反省文を放棄するようになった。
これは、誰がなんと言おうと、良い変化だと思う。
反省文を足蹴にできるようになってから、僕の人生はたまらなく楽しくなった。
人生は短い。筆が進まない反省文を書いている場合ではない。楽しいものを書こう。
あの反骨心を、中学生の僕はしまいこんでしまっただけど、なくなりはしなかった。
数年の眠りを経て、引き出しから飛び出してきた。今の僕の中でも現役で、原動力になり続けてくれている。
いつもありがとう、僕の反骨心。
関連記事

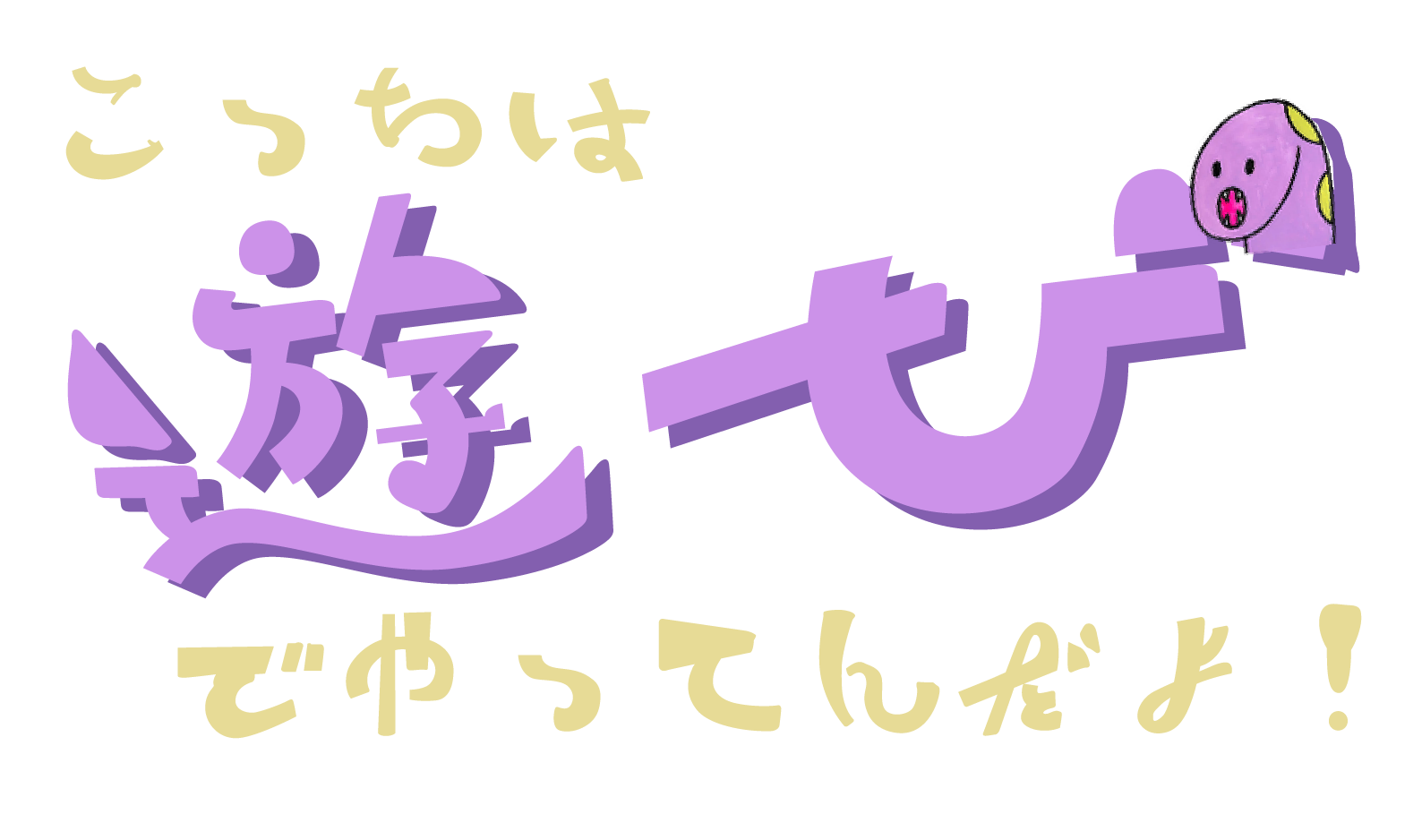
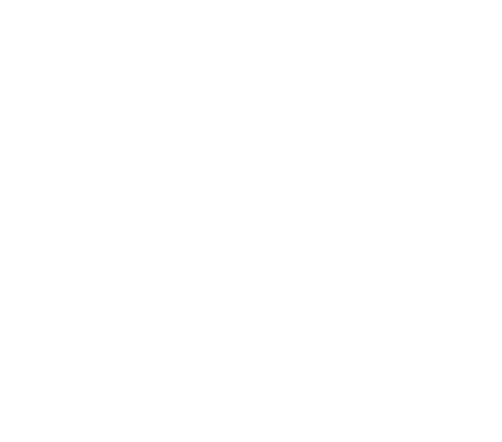
 むだそくんについて
むだそくんについて