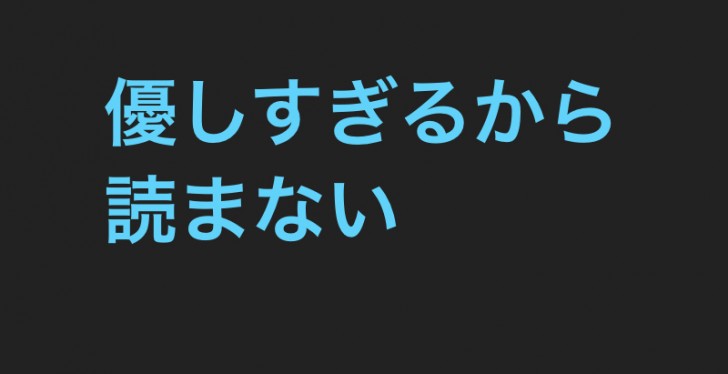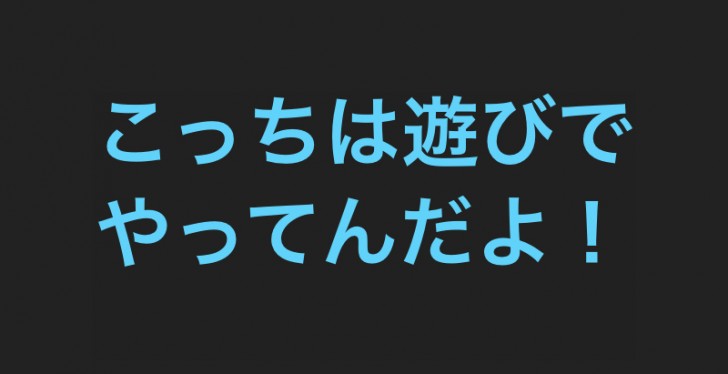インターネット異常者として生計を立てている。
「悪口しか言えない飲み会」だの「旅人と旅人嫌いを戦わせるイベント」だの、謎の企画を量産していたら、謎の理由でスポンサーがつき、謎の理由で生計が立つようになった。
インターネット異常者は、常に「独創的な行動」が求められる。
換言すれば、常に「周囲から浮く」ことが求められる。
そうだ。だから僕は常に、周囲から浮こうとしている。
空気を読んで誰もが聞かないことを、あえて聞く。
「ルールに明記されていないが、やっちゃダメそうなこと」をあえてやりにいく。
「世間でもてはやされてるけどつまらないもの」の、悪口を言う。
そんなことを、繰り返しやった。インターネット異常者としての振る舞いが求められる場所で、僕の行動は称賛された。
そんな生活を、かれこれ3年ほど続けている。周囲から浮こうとする僕の行動はもはや「習性」と呼べるレベルで身についている。
だから、忘れてしまいがちだ。10代の僕は「周囲から浮かないこと」を優先して行動していたことを。
「結婚パーティー」で思い出す。普通の人のこと。

先月、学生時代の先輩から久しぶりに連絡が来た。僕は古い人間関係を長く維持するのが得意ではないので、これは珍しいことだ。
「結婚パーティの司会をしてくれないか」と、頼まれた。
普段、僕はイベント企画や司会進行を含めてお金を頂いているので、司会仕事もタダではやりたくない。「それでしたら◯◯円になります」という見積もりを出したい気持ちに駆られた。
一方で、学生時代に彼にはお世話になったという感覚もある。0.5秒の逡巡の末、「まあ無償でやってもいいな。この人には結構お世話になったし、好きな先輩だ」という結論に達して、「やります!」と良い返事をした。
彼は「ありがとう!」ととても喜んで電話を切り、僕は「爽やかな男だ。彼のパーティが良いものになればいいな」と思った。
当日になった。
「ドレスコードなし。カジュアルOK。司会も同様」という連絡を受けていたので、僕はカジュアルな色つきYシャツとチノパンで参加することにした。
簡単な打ち合わせを済ませ、会場で待機する。受付時間が始まると、パーティ参加者が続々とやってきた。ほとんどは知らない人だが、僕と先輩の共通の知人も何人かいる。知った顔が通るたびに、簡単に挨拶をした。
そんな何人かの知った顔のうちの一人が、僕の方に歩いてきた。髪をしっかりセットして、全身をドレスアップした彼女は、声を上げる。
「堀元じゃん、久しぶり!」
ああ、久しぶりだね、と挨拶を交わす。ちょっとした同窓会のようだ。こんな空気感も、たまには悪くない。
今何してるだの、今日の内容だのという話題を一通り終えて、彼女は僕の服装に言及した。
「それにしてもそれ、カジュアルすぎるでしょ」
僕は答えた。
「カジュアルOKだっていうから。これでも僕にしては、パーカーとスウェットで来なかっただけ空気読んでるんだよ」
「いやいや!絶対浮くって!!私たちだって昨日何着ていくか相談したんだから!◯◯くんも□□くんも、スーツで来るって言ってたよ!」
「うん……。まあ、彼らがスーツ着てきても、別に僕は何も気にならないから。いいでしょ、ドレスコード無いんだからこれで」
「ドレスコードないって言ってもさあ……浮いちゃうよ?常識で言ったらもっとちゃんとしてくるでしょ」
「僕は、常識に縛られないことを仕事にしてるからね(冗談めかしてドヤ顔で)」
「いやいやいや……そこの常識には縛られた方が良かったと思うな」
僕の冗談めかした発言はウケずに空振りに終わり、彼女を呆れさせたまま終わってしまった。
ウケなかったことを残念に思いつつ、僕は懐かしく思っていた。

大学生の頃はしっかり認識していた「ふつうの感覚」を僕はすっかり忘れていた。
そして、僕は彼女との感覚のギャップはもう一生埋められないような気がしていた。
ふつうの人は「浮かない」ことを求められる
「ふつうの」学生だった彼女は、「ふつうの」社会人になっているらしい。
世間で名の通った大学を出て、名の通った企業に就職し、三年ほど勤めてから結婚した。
絵に描いたように順調な社会人生活をしている彼女は、ホントウにすごいと思う。
彼女の「浮くこと」を気にする技術は、社会人生活を送る上で大いに役立っているのだろう。
彼女は、きっと「浮かない」ことを求められ続けてきただろうし、これからも求められ続ける。
僕と会っていなかった数年、適応能力が高くて優秀な彼女は、会社勤めをしながら浮かない能力をたっぷり高めたのだと思う。
「前日までにしっかり、連絡の取れる人と服装のすり合わせを済ませておく」という発想は、彼女にとってはごく当たり前のことなのだろう。
彼女の「浮かない」能力からすれば、そんなすり合わせは朝飯前なのだろう。
僕には、できないけれど。
彼女と話して「ああ、ふつうの人ってこうだったな」と感じた後に、かつては僕も問題なく「浮かない」ことができていたのを思い出した。
「浮かない」ことが美徳だった10代
僕も、10代の頃は、浮かないことを美徳だと思っていた。
中学の選択科目を選ぶとき、親しいグループで何を選ぶか相談した。一人だけ違う科目を取ることなんてできなかった。
高校の文化祭の翌日、出たくもない打ち上げの参加率を気にして、結局参加した。「自分だけ欠席したら角が立つから」と。
大学の新入生歓迎期間、「この期間に動き回った量が大学生活の充実度に直結する」と言われて、面白くもない飲み会に出続けた。薄っぺらい先輩の言葉に愛想笑いするのに疲れて、ヘトヘトになった。
僕も、10代の頃は、「浮かない」で暮らすことができていた。
たしかにあの頃は、「自分だけ違う服を着ている」なんて、ゾッとするほど嫌だったような気がする。
一つ忘れ物をしただけで、ちょっと見当違いの動きをしてしまっただけで、絶望的な気持ちになっていた気がする。
僕は大学二年生の終わりから、少しずつ大学外に飛び出すようになって、異常な活動も少しずつ始めた。学生団体を作って崩壊させたりもした。
「浮かない」という美徳は僕の中から少しずつ失われていき、大学を卒業する頃にはかなり薄れていたように思う。
それでも、大学にいる間は周りの「ふつうの」大学生とそれなりにコミュニケーションを取る必要があったから、「ふつうの」感覚をよく理解していた。理解した上で、意識的に無視しようとしていた。
それが、卒業後は、僕の周りにいるのはインターネット異常者か、インターネット異常者を好む人だけになった。
ふつうの人とコミュニケーションを取ることがなくなり、ふつうの感覚を忘れてしまっていた。
だから、今回のパーティで改めて突きつけられた。ふつうの感覚も、そして、自分がそんなふつうの人だったことも。
浮いても、浮かなくても、生きていける
10代の頃、出たくない打ち上げに出たり、選択したくない科目を選択したりしたことの是非を、今になって考えてみる。
それが辛かったかと聞かれると、正直なところそうでもない。確かに不自由を感じることも多かったけど、絶望するほど嫌だったワケでもない。
僕は、それなりに器用なタイプだ。どんな生き方でも、それなりに合わせることができると思う。
だから、「浮かない」生き方も選択できた、と思う。普通に、それなりに幸せに、波風立てずに生きていくパターンも十分ありえた。
実際、今僕がインターネット異常者になっているのは色々なめぐり合わせが関係している。ほんの少し何かが違えば、僕は今も「浮かない」ことを最優先に暮らしていたかもしれない。
だから、別に「浮かない」価値観の彼女のことを非難する気も、バカにする気もない。感覚の溝は大きいけど、人間としての違いはそんなにない。かつて分岐で一度だけ、違う道を選択しただけだ。
それでも、僕は「浮く」方がずっと幸せだ
ただ、やはり思う。少なくとも僕は、「浮く」暮らしができる方がずっと幸せだ。
今、僕は僕のやりたいように行動している。自分の欲求が、感情が、はっきりとわかる。
これは、幸せなことだ。
心理学用語で「過剰適応」というものがある。
適応という現象は、好ましいものだ。生物は、変化に適応するからこそ生き残ることができる。人間についても例外ではない。人間は多くの環境変化に対して適応することが可能で、引っ越しても転職してもやっていける。
だが、時に人は、適応しすぎてしまうことがある。
自分を少しだけ場に合わせるのではなく、自分の感情や欲求を完全に捻じ曲げて場に合わせることを、過剰適応と呼ぶ。
あの「浮かない」彼女にも、少しだけ過剰適応のきらいがあったように思う。
自分が場に合わせるのはともかく、好き勝手な格好をしていた僕に対して、終始否定的な意志を表明していた彼女は、過剰適応なんじゃないか。
そして案外、「浮かない」を選択した人の多くが、過剰適応に陥るんじゃないか。
自分が何かを着たい気持ちを押し殺して、場に合わせることに徹するから、自分のホントウの気持ちが分からなくなったり、場に合わせないヤツに対して苛立つようになったりする。
人間は、意外にバランスを取るのが苦手な生き物だ。ひょんなことからすぐに、極端に走ってしまう。
「ちょっと合わせておこう」だったつもりが、過剰適応に陥ってしまいがちだ。
僕も「浮かない」生き方を選んだら、過剰適応していたかもしれない。
それは嫌だな、と思う。
自分の欲求を見つめて、尊重できる今の暮らしが好きだ。
何かに合わせることなく、自分の欲求の通りに行動できる、今の暮らしが好きだ。
だから、僕はこれからもインターネット異常者として生き続ける。
空気は読まないし、いろんなものに噛み付くし、誰もやってないことばかり挑戦する。
「浮く」ことが美徳の世界で、浮いた生き方をし続けようと思う。
出たくもない打ち上げに出て、浮かない顔をしていた10代の僕へは、もう戻らない。

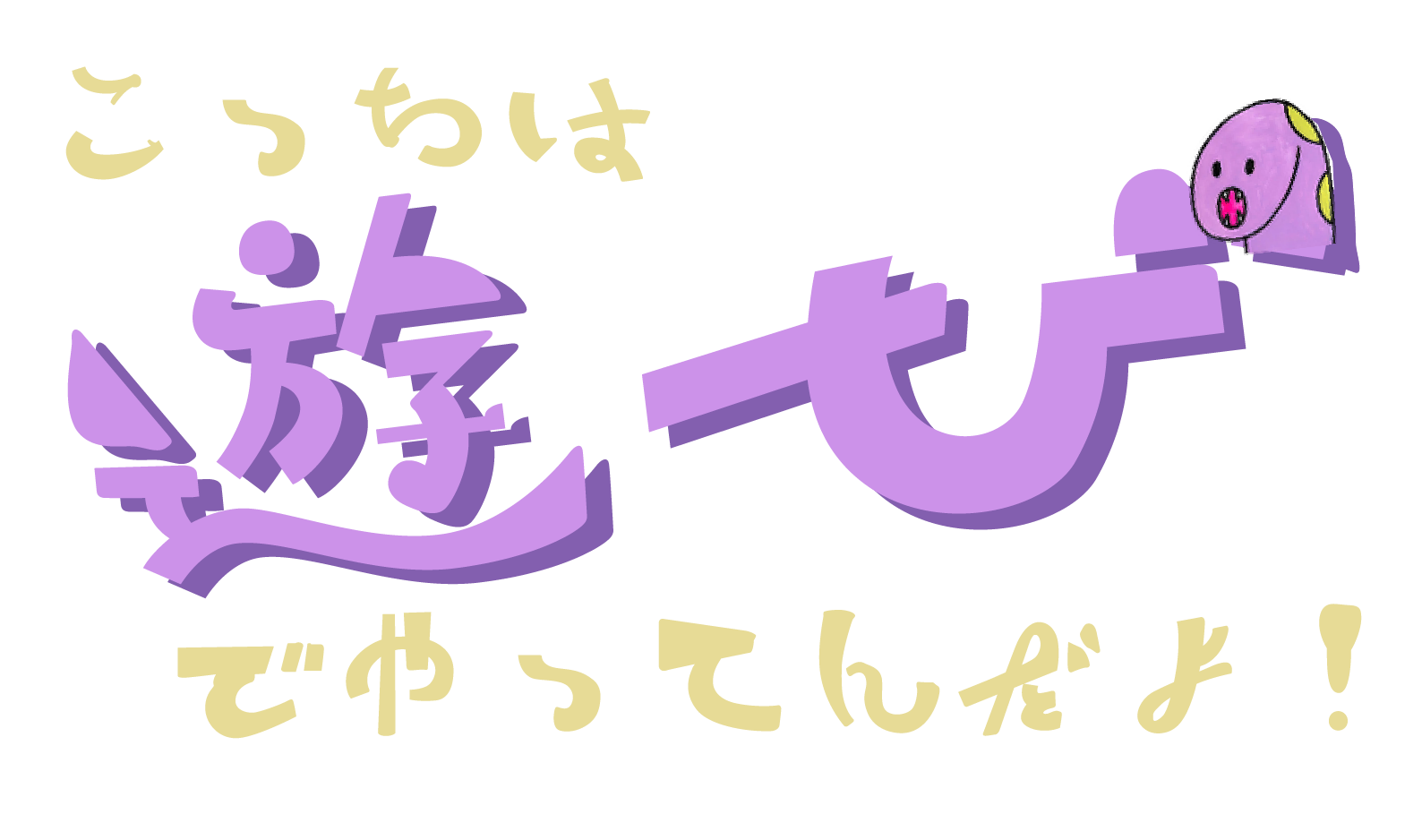
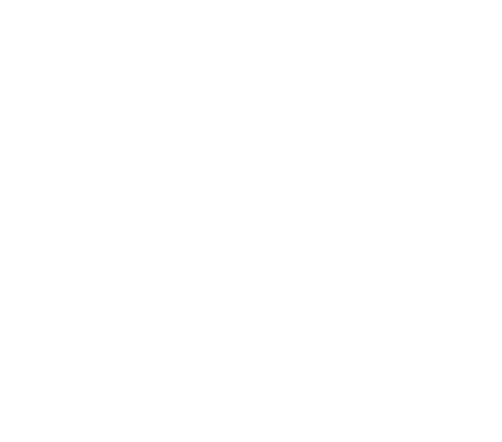
 むだそくんについて
むだそくんについて