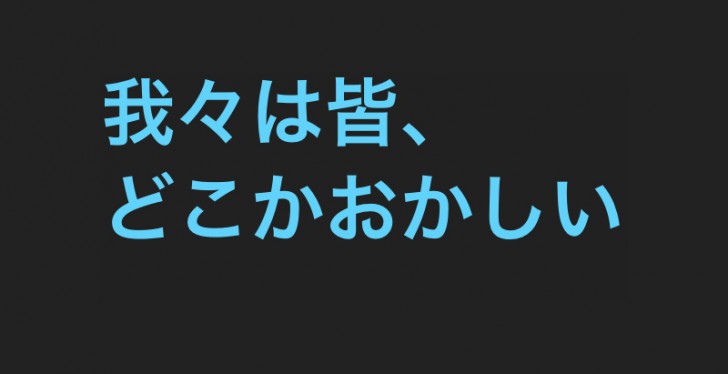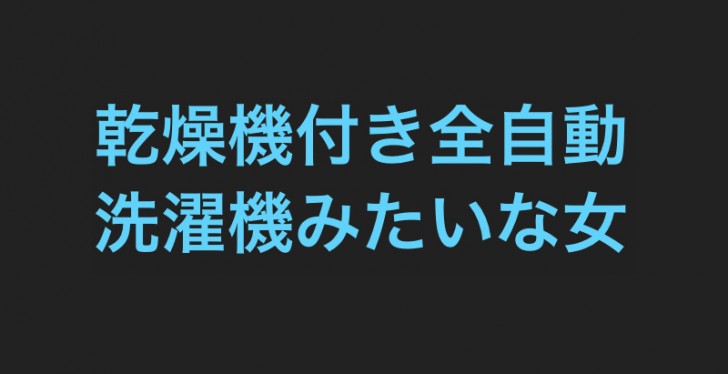こんにちは。堀元です。
街がクリスマスムード一色で、浮かれてしまってあまり仕事をやる気が起こりません。
ブログも、ビジネス論みたいな堅苦しいものだと書く気が起こらないので、なんかユルい記事を書こうかなと思います。
で、せっかくなのでクリスマスのエピソードかな、と考えまして、去年のクリスマスイブにデートをすっぽかされて悲しかった話を書こうかなと思ったのですが、やめます。(底抜けに悲しいだけで終わりそうだからです)
で、なんか逆に、ある暑い夏の日のエピソードを書いてみようと思いました。
ホームレスに間違われながら夜を越した高校時代の話です。お付き合いください。
ボスドンマラソンと旅立ち
高校一年生の夏だったと思う。僕たちは典型的なやることのない高校生だった。
部活に精を出すわけでもなく、勉強を頑張るわけでもなく、彼女もいない。
ついでに言えば、これと言った趣味もないし情熱もない。
しかし、誰にでも平等に夏休みは訪れる。あれ、なんか名言みたいになった。当たり前のこと言っただけなんだけど。
まあとにかく、そんな高校生であった僕とTくんは、日夜積極的に時間をムダにしにいっており、太鼓の達人というゲームについているミニゲーム「ボスドンマラソン」を8時間連続でプレイするような毎日を送っていた。

そこには確かに青春があった。ボスドンマラソンを必死でプレイし全力でしのぎを削った夜のことを、今でも時々思い出す。
それがどんなに馬鹿げたことであったとしても、16歳の少年が何かに夢中になることは、青春だ。
高校球児だろうが自堕落な高校生だろうが、誰にでも平等に青春は訪れる。ダメだこのフォーマットにハマった。何でも名言みたいになって便利だ。
まあともかくそんな中、不意に「そうだ。自転車で100kmくらい旅行してみよう」と、僕は思い立った。ボスドンマラソン内で走る太鼓に触発されたのかもしれない。
多分にいきなりではあったけれど、一緒にボスドンマラソンで夜を明かした朝、Tくんに言った。「今から自転車でどこか遠くに行かないか」と。
青春とは、待てないことであるように思う。僕はこの時、一秒も待てなかった。
大人になった今、こんな発言はできない。自分にも相手にも予定があり、誰かと旅行に行くのは、日程調整を丁寧に行うところから始まる。
16歳の僕は違った。待たない。待てない。今から行こう、と言った。これはすごく尊いことだ。あれから10年近いときが経ち、僕はもう「今から」を言えないのだから。
どうせ、僕もTくんも今日の予定がないのは分かりきっていた。スケジュール帳の確認など必要ない。どうせ毎日まっさらだ。
僕は返事を聞くまでもなく、今すぐに旅立つことになる。そう確信していた。
Tくんは答えた。構わないけど、眠いからちょっと寝てからでもいいか、と。
Tくんは僕よりも大人だった。Tくんは待てた。先ほど「青春とは、待てないことである」みたいなことを言ったが、前言撤回だ。青春とは、己の欲望に対してまっすぐであることだ。
Tくんは睡眠欲に対してまっすぐだった。よく考えたら徹夜明けだから、僕も眠い。
「それじゃあ、少しだけ眠ってから出発しようか」
その日は出発できずに、夕方まで寝てしまったことは言うまでもない。
翌日、気を取り直して僕たちは出発した。目的地は、美唄という小さな町にした。僕の実家がある札幌からはおよそ63kmくらい。まあ100kmには遠く及ばないのだけれど、あまり細かいことは気にしないことにした。
僕たちは、何も決めずに漕ぎ出した。なんとなくの方向だけを調べて、ママチャリでひたすら進んだ。
寝る場所や、食事をどうするかなどは一切決めていない。完全なノープラン。自転車で遠出をするのも初めてなら、こんなにノープランの旅行も初めてだった。胸が踊った。
どこまででも行ける気がした
空が青い日だった。僕は夏の青空が好きだ。
北海道の夏は短い。真夏らしい気温かつ晴れ晴れとした天気の日は一年に20日くらいしかないように思う。
川沿いの道を、一息に自転車を漕いで進んだ。ほんの40分も漕げば、普段見ない景色ばかりになる。
2時間くらいで、札幌の隣町、江別の噴水がある公園についた。真夏日で、子どもたちが全身水浸しになって遊んでいた。
僕とTくんはその子どもたちの様子を眺めつつ、自分たちも少しだけ水を浴びた。先は長い。あんなに水浸しになるわけにはいかない。しかし僕たちも水を浴びたい。
そんな葛藤も青春なのだと思う。
中途半端に水をかけあうところから始まり、結局僕とTくんは水浸しの状態でそこからの道のりを進むことになった。
法が人を守るのか、人が法を守るのか
岩見沢は、典型的な地方都市といった様相の町だ。札幌からは50km弱くらいだろうか。
駅前から伸びる通りはシャッター商店街で、国道沿いにはやたら大きなファミレスが時々ある。
日本中にある、均質化された地方都市の風景。
僕とTくんがそんな岩見沢に到着したのは、21時を回った頃だった。一日で美唄まで到達するのはもう無理だ。足はガクガク、お腹はペコペコ。今日はここを終着点とするべきだ。二人とも言葉には出さずとも、その合意に達していた。
泊まるところをどうしようかと考える。縁もゆかりもない地方都市、岩見沢。勝手も分からない上に、宿泊施設の選択には大きな制約がつきまとっていた。
何しろ我々は16歳だ。お金がない。
財布に入っていた金額だけを握りしめて出発したから、手元には5000円くらいしかなかった。Tくんもほぼ同様の条件。
今後の食事などもここから賄うのだから、あまり無駄使いはできない。
結局、僕たちが選択できる宿泊場所などネットカフェくらいしかなく、岩見沢に唯一あるネットカフェの自遊空間に向かうことになった。
「お客様、18歳以上ですか?」
気だるそうなバイトの兄ちゃんにそう聞かれたとき、僕たちは雲行きの怪しさを感じた。
「16歳です!」と堂々と答えると、「あー、条例の問題で、18歳以下は宿泊できないんすよね」と、やっぱり気だるそうに言われた。
「間違えました。やっぱり18歳です」とダメ元で言ってみたけど「じゃあそれを証明できる身分証明書を提示して下さい」と言われた。完全な手詰まりだった。
しかし僕らとて引き下がるわけには行かない。泊まる場所はここしかないのだ。
「何とか入れてもらえませんかね?僕ら今日泊まるところもないんですよ」と、人情にうったえてみた。
「そんなこと言われても。青少年保護育成条例がありますから」と言われた。
青少年保護育成条例のせいで、僕たちは寝るところを失った。皮肉な話だ。
青少年保護育成条例とやらは、青少年を保護してくれないのだ。行き場のない青少年を、ネットカフェから追い出すために存在している。
普通に考えれば、泊まる場所のない16歳を追い出す方がよっぽど不健全で危険な行為のはずだ。青少年の健全さを守るためには、ネットカフェに泊めるべきに決まってる。
僕はこの時はじめて「法が人を守るのか、人が法を守るのか」という議論にぶつかった。
法が人を守るべきであり、人が法を守るべきではない。僕の揺るがぬ倫理観は、この瞬間に生まれたと思う。
看板が蛾で読めないびっくりドンキー
それにしても、均質化されているはずの地方都市である岩見沢は、この時異常事態を迎えていた。
それは、「蛾の大量発生」だ。この年、岩見沢は未曾有の蛾の大量発生に悩まされていた。
どのくらいすごかったかというと、ファミレス「びっくりドンキー」のほとんどの文字が蛾で埋め尽くされて、「び……ン……」としか読めなくなるくらいだ。
光る看板は、走光性を持つ蛾を集めまくり、街中のあらゆる看板は読むのが困難になっていた。「看板の文字が涙で滲む」というような修辞法はあるが、この時は蛾で滲んでいた。叙情的と言えなくもない(言えない)
そんな大量の蛾が集まっては死んでいく地獄のような光景の中で、ファミレスの店員は淡々と蛾の死骸を処理していた。
ホウキとチリトリで蛾を集めて、ゴミ袋に詰め込んでいく。慣れた動作だった。後から調べたところ蛾は一週間前から大量発生していたそうだ。既にバイト達のルーチンにも組み込まれていたのだろう。バイトは特別な感慨を持った様子もなく、ひたすらチリトリに蛾を集めていた。
そんなバイトの動きを見ながら、僕たちは考えていた。もう、野宿するしかあるまいと。
ネットカフェを追い出されてから、何件かの宿泊施設に電話を入れた。しかしことごとく、留守電になっていた。21時以降、新規の宿泊客を受け入れる施設など、岩見沢には存在しないのかもしれない。
ホームレス呼ばわり
”野宿”という単語にはある種の憧れと恐怖が宿っている。
しょっちゅう聞く単語でありながら、実行する人は恐らくそう多くない。そんな感じ。
でも僕たちはそのことに逆にテンションが上がった。人生で一度くらい、野宿ってやつも経験しておくべきなんじゃないかな。何事も経験だろ?
岩見沢をしばらく自転車で走り回りながら、野宿できそうな場所を探した。
20分くらい走り回った後、僕たちはある公園を見つけた。
◯◯森林公園みたいな、大げさな名前がついているわけではない、ただの市民の公園。
それなのに、やたら大きい。400平米は余裕であるだろう。地方都市だからこそ可能な土地の使い方だ。
公園の端にはSLが展示されていて、遊具の類も充実していた。
しかも、うってつけなことに、チューブ状の遊具もあった。ドラえもんの空き地のドカンのように、中に入って過ごせる遊具だ。
ここなら、野宿してもいいんじゃないか?自然とそんな空気になった。
公園の中に人目は少ない。
黙ってベンチで酒を飲んでいるオッサンが一人。同年代と思しき少年少女の5人組。それぞれ、ずっと遠くにいて、それぞれの世界に入っていた。
彼らを尻目に、僕たちはチューブに入る。
チューブの中は広かった。二人分の身長を合わせた長さよりも少し長く、僕たちは二人で縦に並んで寝ることにした。
足を外側に向け、頭を内側へ。僕たちは二人ともその向きで寝そべり、カバンを枕にした。
頭と頭の距離は近い。小声でも会話ができる。
「このチューブ硬いな。背中が痛い」
「俺、着替えのTシャツを背中に敷いてみたよ。だいぶマシだ」
「なるほど。俺もやろうそれ」
「それにしてもケツが痛い。チャリずっと乗ってるとキツいな」
「そうだな。電車で来ればよかったな」
「今回の趣旨、全否定しちゃったよ」
チューブの中、お互いの声はくぐもって聞こえる。不思議な安心感があって、面白い空間だった。
そんな中、外から不穏な会話が聞こえ始めた
「さっき入っていった……」
「そんな……二人……」
「……マジで……ホームレスだよね」
僕たちは断じてホームレスではない。短い10代の夏を謳歌している君たちと同じように、僕らには夢があり社会生活があり、もちろん家もある。
まあしかし、街灯の少ないこの公園で、チューブに入っていく僕たちの容貌は彼らからはほとんど見えなかっただろう。僕たちも彼らの顔は見えておらず、声のトーンでおおよその年齢を判断したのだから。
だから、彼らが僕たちを、行き場のないオッサンのホームレスだと誤認したとしても仕方ない。先程の僕らの軽妙なトークを、彼らは全く聞いていないのだ。(チューブ内で小声だったから)
自分たちの噂をされているのを感じながら、僕たちは無言でチューブ内に居続けることを選択した。
嵐は去る。彼らのエンターテイメントとして消費されることに甘んじよう。好きなだけホームレスだと思えばいい。
しかし、ここで事態は悪化する。
「お〜い!そこ寝るところじゃないですよ〜!」
なんと、一人の少年がチューブ内の我々に話しかけてきた。声は遠い。100m先だ。会話していた場所から動かず、おもむろにチューブに向けて叫び始めたのだ。
声には聞き覚えがある。少年少女の集団の中で、最も大きな声で会話を牽引していた一人の少年だ。恐らくお調子者で、恐らくヤンチャで、こういうときに堂々と絡みに行けるのがカッコいいと思っているタイプだ。
こういうタイプは、学校には来たり来なかったりで、いつも気だるそうに授業を受けて教師たちの手を焼かせ、そのくせ体育祭のときにはハリキるのだろう。あいつら学校嫌いなクセになんで行事の時は人一倍ハリキるんだ。情緒不安定か。いつもはそっけないのに、たまに好意をアピールしてくる少女漫画の本命男子タイプか。ところであの少女漫画の定番の構成はよくない。一途でめちゃくちゃ優しくて経済的にも安定している男は最終的にフラれて、フラフラしてて粗暴で気まぐれの塊みたいな男がヒロインに好かれるやつ、あんなものがまかり通ってたらたまったもんじゃない。あの構成どうにかしろ。
話が大いに逸れてしまったので少女漫画の話をやめて本筋に戻すと、まあそんな風に一人の少年が僕らに話しかけてきたわけだ。
どうしようかなと思いつつ、やはり僕たちは無言を選択した。もう寝たことにしよう。都合が悪いことをスルーするのに、「寝たことにする」というツールは非常に有用である。
「お〜い!聞いてる!?」
……
「お〜い!ホームレス!!」
……
「そこで寝たらダメだよ〜!警察通報するよ!!」
……
カンッ!
何を言われても寝たふりを維持しようと思っていたのだが、「カンッ!」という小気味いい金属音だけは、サスガに無視できない。
それは、僕らが寝ていたチューブ状の遊具に小石がぶつかった音であり、すなわちお調子者の少年が小石を投げるという物理的な攻撃をしかけてきたことを示していた。
実に腹立たしい。何が「警察通報するよ」だ。警察のお世話に近いのは明らかにお調子者の君であり、自堕落ながらも問題行動をそれほど起こさない僕たちではない。っていうかあいつらすぐ「警察呼ぶぞ!」って言ってくるの何なんだ。粗暴なヤツほどすぐ「警察呼ぶぞ!」を持ち出してくる。普段違法行為に手を染めているときは警察を恐れるクセに、揉め事の際にすぐ警察を呼びたがる。情緒不安定か。いつもはそっけないのに、たまに好意をアピールしてくる少女漫画の本命男子タイプか。ところであの少女漫画の定番の構成はよくない。一途でめちゃくちゃ優しくて経済的にも安定している男は最終的にフラれて、フラフラしてて粗暴で気まぐれの塊みたいな男がヒロインに好かれるやつ、あんなものがまかり通ってたらたまったもんじゃない。あの構成どうにかしろ。
再び話が逸れてしまったので少女漫画の話をやめて本筋に戻すと、結局僕たちはチューブから出ていくことにした。
「ホームレスを公園から追い出す俺。勇気あるだろ?」という自己陶酔に入ってしまった少年は、中々この自己陶酔から抜け出さないだろう。
最悪、近づいてきてチューブを覗き込む可能性すらある。それは避けたい。
まだ距離がある時点で、チューブから抜け出して移動するのが正解に思えた。先程聞こえた声からすると、まだまだ顔が見えないくらいの遠くにいることは間違いない。
荷物を素早く回収してカバンに詰め込み、チューブから出て、自転車にまたがった。
「あっ!出てきたww」という嘲笑を背中に受けながら、僕たちは公園を後にした。やっと手にした安息の地だったのに……。聖地を追放されるユダヤ人の気持ちが、少し分かった気がした。
ネオンに引き寄せられる
結局、あの公園以上のスポットは見つからない。
何より、人生初の野宿に失敗したことで、僕とTくんのテンションは下がっていた。
行く宛てのない僕たちは、国道沿いでひときわ明るい光を放つ店に吸い寄せられた。「びっくりドンキー」だ。この店のネオンは、蛾のみならず野宿に疲れた僕たちをも引き寄せるらしい。
先ほどよりもさらに蛾が集まってきていて、もう看板は「………ン……」となっていた。かろうじて「ン」が読めるか読めないか。
考える力もなく僕たちは店に入った。時刻は夜中の1時。
普段はこの時間に客が来ることなど無いのだろう。店員は驚いた顔で僕らを見た。
入店拒否されたら嫌だな、と思ったが、店員はすぐに「いらっしゃいませ。二名様ですか?」と、テンプレの一言を口にした。よかった。
ネットカフェと違って、びっくりドンキーは僕らにも門戸を開いてくれた。
誰にでも平等に、びっくりドンキーは訪れる。あ、ダメだこれは。何でもイケるかと思ったけどこれはダメだった。名言感ゼロだ。今のなし。
ともあれ、テキトウなメニューを注文し、僕たちは安息の時間を得た。
僕とTくんは、夜が明けるまでここにいる覚悟を決めた。
店は24時間営業だ。僕たち以外の客は誰もいない。長居をするのは精神力を問われるが、また野宿の場所を探しに旅立つよりもよっぽど気楽だった。
ファミレスで、時間を一秒ずつ浪費していく。自堕落な僕たちに似合いの、自堕落な時間。
それでも僕は思った。「少しでも寝ておこう」と。
Tくんと協議の末、「店を追い出されないように寝る方法」に思い至る。その手法は至ってシンプル。
一人ずつ、机に突っ伏して寝るというものだ。
「僕は起きてて、スマホをいじっているのですが、友人は寝てしまいました。スマホをいじる用事が終わったら起こして店を出ますからね」的な空気を出すことができる。
朝まで、この作業を延々繰り返した。甘党のTくんは時々、いちごパフェを追加注文していた。注文を取りに来る20歳くらいのバイトが「この少年たちは一体どういうつもりでここにいるのだろう」という顔をしていたのをよく覚えている。
朝5時、太陽は出ていないが周りは明るくなっていた。
真夏とはいえ、北海道の朝は寒い。長袖のパーカーを着て、僕らはびっくりドンキーを出た。
かすかに朝もやがかかる中、街が動き出しているのを感じた。
朝の到来を嬉しく思った。これでまた、どこにでもいける。
身体は疲れていたが、心は躍り始めている。そうだ。僕たちの旅はまだ途中だ。ここから先、どんなワクワクが待っているのだろう?
僕はTくんに言った。「さあ、朝が来た。行こう。目的地はまだ先だ」
16歳の少年は燃えていた。今すぐに出発したい。今すぐに自転車を漕ぎ出して、新しい景色を見ようと思った。
Tくんは答えた。構わないけど、眠いからちょっと寝てからでもいいか、と。
Tくんは僕よりも大人だった。相変わらず、睡眠欲に対してまっすぐだった。よく考えたら、いや、よく考えるまでもなく僕も眠い。
「それじゃあ、少しだけ眠ってから出発しようか」
その日は出発できずに、夕方まで寝てしまったことは言うまでもない。
ちなみに、眠ったのは入店拒否をされた自遊空間だった。青少年保護育成条例によって入店できないのは朝5時までだったから、もう条例に縛られる必要はない。
夜勤明けの眠そうなバイトの兄ちゃんが「またこいつら来やがったよ」という顔をしながらダラダラと入店処理をする様子を、今でも時々思い出す。
こんな、オチがあるわけでも示唆に富んだわけでもない、でも時々思い出してしまう青春の夏の一日は、きっとだれにでも平等に訪れるのだと思う。

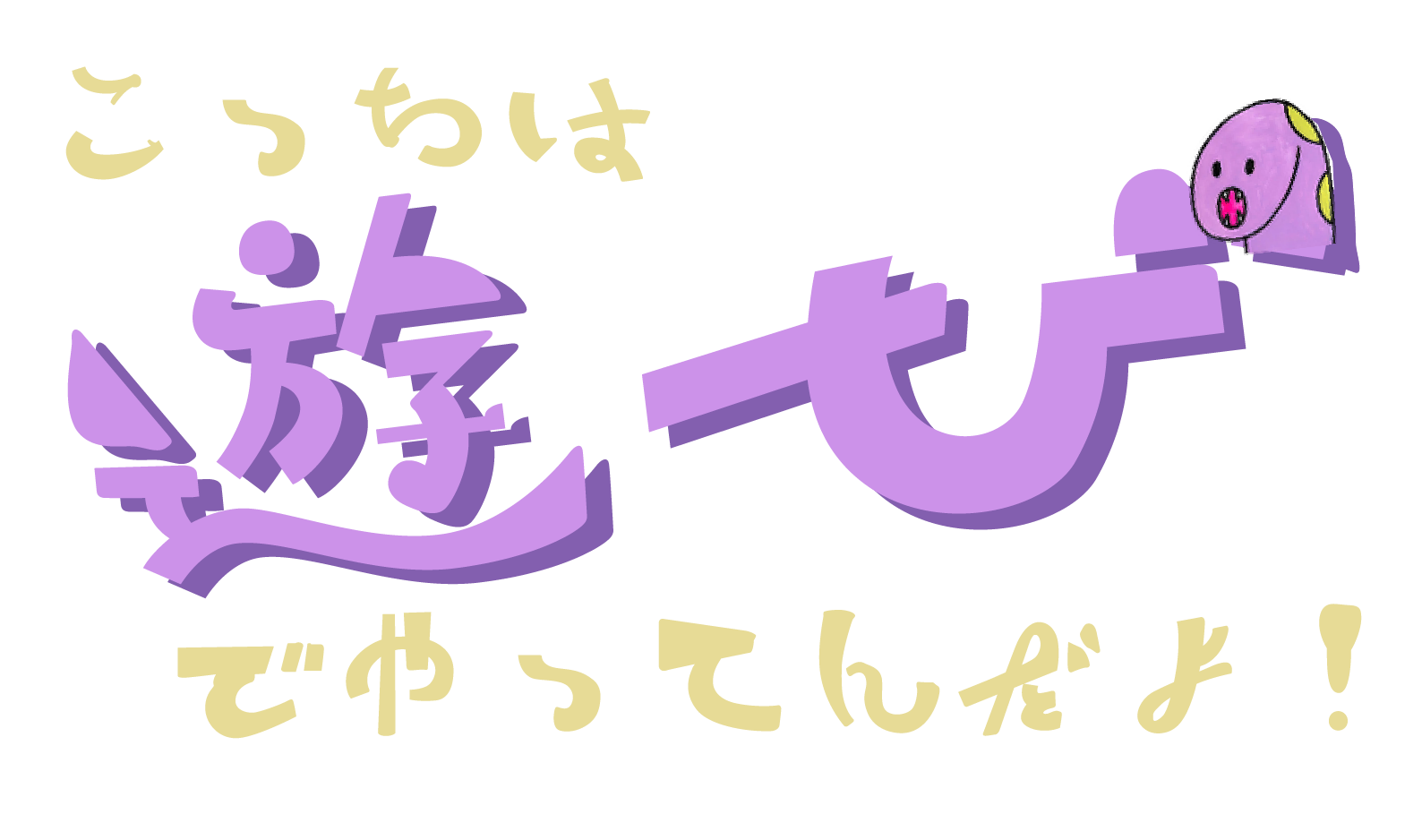
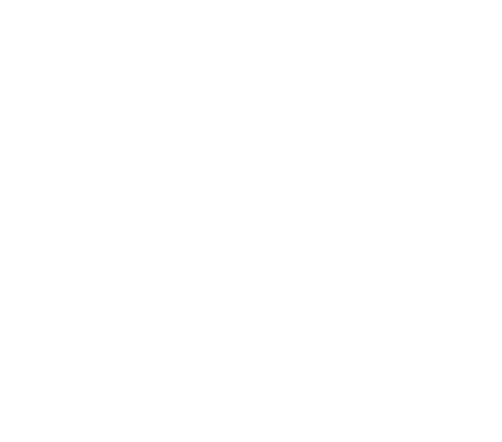
 むだそくんについて
むだそくんについて